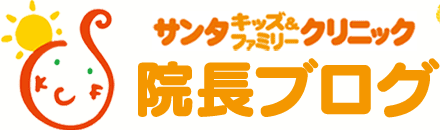「無事国家試験も合格し
医師としての
小児科医としての第一歩を
九州大学病院でスタートしました。
医師免許をいただいたとはいえ
まだまだと言うか
実践力は全く0の状態でのスタートでした。
病棟で
小児癌のこどもたちの主治医に
なりましたが
こどもたちは、とても苦しい治療を受けてきて
僕たち研修医が何もできないことを
患者さん自体、親御さんもわかっています。
薬一つ出す
熱冷まし一個出すのも
風邪薬を出すのさえ
指導医に確認し
自分ひとりでは何もできない状態の研修医。
僕にできることは
こどもたちと遊ぶことでしょうか
そんな僕を
先生と呼んでくれていたのは
立派な先生に早くなって
僕を1日でも楽にしてねと
病気をしていても天真爛漫の笑顔の奥にある
ふとみせる悲しい表情が忘れずに
研修医なりに持ってる知識を総動員し
もっと、もっと学ばないとと
患者さん、病気と24時間休みなしで
向き合って過ごしました。
でも
こどもたちが笑顔で元気になって退院しても
なかなか医師としての実感を感じられませんでした。
僕が描いてた医者の像との乖離を感じ
治した実感がありませんでした。
薬が、あの20mlの薬液が、ちっさい、ちっさい丸薬が
治しただけで
僕はこどもたちに何ができただろうか?
もっと医師として
この手で、我が力で
病気を治したいと思うようになりました。
その時の思いが
僕の今の医療スタイルにつながっているのには
間違いありません。
現代医学の礎、考え方をを今に伝えている
医聖ヒポクラテス(BC450-300)が次の言葉を残しています。
「病気を治すのは
医師ではなく自然である。
医者はそれを手伝うだけだ」として
自然治癒力を重視したという
言葉が残されています。
医者が治しているのではなく
治すお手伝いをしているだけ。
僕が研修医の時感じた思い
現在に続く思いは
間違いではない。
患者さんの治癒力を引き出すために
僕ができることをすればいいんだ。
今でも医師としての道は途中。
まだまだ僕の歩む医道は続きます。」
今もその思い、気持ちは変わりません