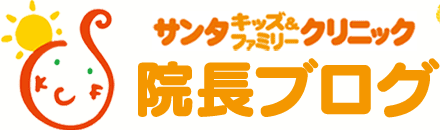検索
カレンダー
-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
リンク
「今日の言葉」カテゴリーアーカイブ
人生3万日
人生80年を生きる日を
日数でいうと約3万日ということになり
5千日ごとにその年齢に応じた役割があるのです。
生まれてから14歳までの5千日は
ひたすら「感謝」のこころを育てる時期。
次の27歳までの5千日は
がむしゃらに「学ぶ」時期。
更に41歳までの5千日は
学ぶことを「実践」する時期。
それから55歳までの5千日は
己の人生を「構築」する時期。
その次に訪れる68歳までの5千日は
今まで得た集大成を後に続くもの達へ
「還元」する時期。
そして、80歳までの5千日は
ここまで生かしてもらった社会に対する
「奉仕」の時期なのだというのです。
こういう区切りを頭に置いて生きると
人生の生きる目的が見つかりやすいですね。
カテゴリー: 今日の言葉
人生3万日 はコメントを受け付けていません
黒川の女達
この映画は
1930~340年代、政府の国策のもとでおこなわれた
岐阜の黒川村から満州の地に渡った開拓団が
生きて日本に帰るために
18歳以上の未婚の女性に接待をさせた。
みなが生きて帰るために
文字通り体を派って、辱めにも耐えて
生きて日本に帰ってこれたのに。
彼女に待ち受けていたのは
差別と偏見の目立ったのです。
彼女達も
生きていくために
当時のことは封印し生きてきたのです。
でも、当時のことを
「なかったことには
できない」と
当時の事実を語ったドキュメント映画。
事実は小説よりも奇なりという。
まさに
今平和で生きていけるのは
出征した兵隊さんのおかげだけでなく
歴史の闇に葬られた
このような女性の戦いもあったことを
忘れてはいけない。
この秋
これからの国のリーダーになる人の
演説を機会が多くあったけど
いつも
靖国神社の参拝が取り上げられる。
そこにはA級侵犯だから・・・とか
そこを問題にしているが
もっと、もっと大きな広い目で
日本のためにいのちを捧げた人々に
純粋に感謝の気持ちで
手を合わせないといけない
と思う映画でした。
カテゴリー: 今日の言葉
黒川の女達 はコメントを受け付けていません
悟るとは?
前回のブログで
太宰治は「パンドラの箱」の中で
人間は死によって完成されると
書いてあることについて
書きました。
同じ文豪であられた
正岡子規が病床にいたときの
日々の思いを書き留めていた
「病床六尺」の中で
悟りについて書かれた箇所があります。
「悟りといふことは
いかなる場合にも
平気で死ぬること思っていたのは間違いで
悟りといふことは
いかなる場合にも
平気で生きていることである」と
書いています。
つまり
悟りとは
自分がどう生きていくべきかを
何か修行をして気づくことではなく
日々の生活の中で気づくこと
今を生きること
すなわち、今を生きていること全てが
悟りなんだと思う。
悟りとは
何を悟るのか?
生きている日々の中で
何を感じたときに悟ったと思うのだろう?
僕は
悟りは学ぶものでもなく
人から教えてもらうものでもなく
こころで感じるものではないのかと思う。
こころで感じたものは
きっと魂が学ぼうとしたもの
現世に生まれてきた目的
そして魂の学びを感じられたときに
悟ったと思うのではないのでしょうか。
僕も
病気をして
全てを失ったときに
自分の生活、生き方に向き合い
「愛」の大切さを知りました。
「愛」を学ぶために
この世に生まれているのだと思います。
だから
今もこうして思い、感じたこと
つまり僕の感じた小さな悟りを伝えたくて
毎日ブログを綴ってえるのだと思います。
今の生活、今生きている瞬間
全てが悟りの瞬間なんです。
そんな悟りの時間を
大切に愛を込めて過ごすことで
自分の生きていく道、つまり悟りの道が
広がっていくのだと思います。
カテゴリー: 今日の言葉
悟るとは? はコメントを受け付けていません
死によって完成する
生きるとは何か
死ぬとは・・・・
この永遠の命題について
昔から
多くの哲学者を始め知識人が考え
各々の考えを残しています。
昭和の文豪太宰治は
著作「パンドラのはこ」の中で
こんな風に語っています。
「人間は死によって完成せられる
生きているうちは
みんな未完成だ。
でも、虫や小鳥は
生きて動いてるうちは完璧だけど
死んだ途端にただの死骸だ。
完成も未完成もない
ただの無に帰る。
人間はそれに比べると
まるで逆である。
人間は死んでから、1番人間らしくなる
というパラドックスも成立するようだ」と。
つまり
今生きているのは
何か目的をもち
自分を成長するために生きていると
太宰は考えたのだろうか?
死は終わりではなく
死をもって生きて経験したことが
意味をなす。
肉体以外に魂があること
魂の成長のために
生きているのだと言っているのか?
太宰治は
破天荒な人生を生きた方のように
僕は思うのが
何かの成長を意識して
生きてこられたのかもしれない。
太宰治が
魂のことを信じていたかどうか
確認する術は
今の僕にはないが
きっと人は
魂を持ってこの世に生きていて
死ぬと、肉体は死骸だけれど
魂はその後もいきると
考えていたのかもしれない。
太宰治の話を聴くことができるなら
是非きいてみたい。
あなたは、魂の成長を意識していきていたのですか?と
カテゴリー: 今日の言葉
死によって完成する はコメントを受け付けていません
遠い山なみの光
人は希望と夢を持っているから
生きていけるだ。
ノーベル賞作家カズオイシグロ原作の
映画をみた。
カズオイシグロは長崎出身である。
過去の長崎と現在のイギリスとを
人生を描きながら話しを進んでいく。
長崎で原爆を経験した
二人の女性のその後を描いた人生。
被爆地にいたことで
原爆の恐怖、周りの偏見、将来の不安を
抱え生きている二人の女性。
新しい希望を描いて
外国で生く決断をした二人。
しかし、そこでも苦しい現実が待っていた。
戦争が
どんなに深く傷跡を残し
運命を変えてしまう。
でも、生きていかないといけない現実。
平和について改めて
考えさせられた映画だった。
カテゴリー: 今日の言葉
遠い山なみの光 はコメントを受け付けていません
こころがこもった言葉
南極観測船「ふじ」に乗り込んでいる
夫に宛てて
日本にいる奥さんが打った電報は
ただ3文字「ア ナ タ」。
たった3文字の言葉だけど
その言葉に込められた思いが
当事者でなくても伝わり
奥さんの夫を思う気持ちがヒシヒシと伝わってくる。
人は言葉を使うことで
多くのことを人に伝えることができるようになった。
そして
現代は、本、手紙、電報、作文だけでなく
SNSを使って
今感じることを文章で伝える手段を多く持つようになった。
実際
直接話すよりも
文章で思いを伝えることが増えてきた。
かつては
目を見て話しなさいとよく言われた。
発する言葉が相手に伝わるように。
でも今は
どんな文章を書く時には
「こころを込めて」書くことが大事になってきているような
気がするのです。
カテゴリー: 今日の言葉
こころがこもった言葉 はコメントを受け付けていません
清少納言
清少納言といえば
「春はあけぼの・・・」ではじまる
「枕草紙」の作者で有名です。
実は幼い時父・清原元輔が
周防の国司になられ、現在の防府市にあった
周防国府に赴任されていたようです。
自分が今生きているところに
1200年前の超有名な女流作家がいたなんて
とても浪漫を感じてしまいます。
ただ清少納言は
清原元輔の晩年にできた子で
赴任を命じられたのは974年。
清少納言は966年頃生まれたと言うことなので
清少納言が当時のこと(思い出)とわかることを
残念ながら書き残してはいません。
ただ「枕草紙」160段に
「ただ過ぎに過ぐるもの 帆かけたる船。
人の齢。春、夏、秋、冬」という
文章を残しています。
この文章は
おだやかな海をゆったり
帆をあげた舟に乗っている時のことを思いだして
書いているのでしょうか。
すれ違う船はどんどん過ぎていく。
きっと瀬戸内海を
父親と乗った時の楽しい思い出を思いだし
きっと
今は自分もおとなになり
もしかしたら父親も亡くなっているかもしれない
そんな時間の流れを感じたのでしょう。
きっと
清少納言にとって
防府にいた時は
父親と過ごした楽しい思い出の時間だったことでしょう。
カテゴリー: 今日の言葉
清少納言 はコメントを受け付けていません
善く生きるとは
僕たちがこの世に人間として
この世に生まれてきたからには
他の動物のようにただ生きるだけでは
生まれてきた理由
生まれてきた使命を果たしたと
言えないのではないのだろう?
どう生きてきたかが重要で
善く生きてこそ
人間としての使命が果たされたとも
言えるのです。
そして「善く生きる」とは
自分自身の満足するためだけに生きるのではなく
自分以外の人たちや
社会全体の幸福や喜びを考えて
行動することだと思うのです。
人間は
誰かの喜びを創るべく生き、
誰かの喜びを生み出したことにしあわせを感じるのです。
カテゴリー: 今日の言葉
善く生きるとは はコメントを受け付けていません
人は誰かと見守られて生きている
人は
ひとりでは生きていない
ひとりでは生きられないとも
よく言われます。
確かに
人は特につらいときは
誰かが見守ってくれている
自分の元気になるように
願って祈って下さっていると思うと
どんなに力づけられることでしょう
そして
一歩、一歩前に進むことができるでしょう。
僕も入院したとき
家族が、スタッフが
他にも回復を願ってくれる方々の
無心の祈りによって
病から回復し
また今ここにいられると思っています。
人の思いに助けられたのは間違いないのですが
忘れてはいけないのは
僕をどんな時も、守ってくれていた
自然の力があることを知りました。
入院して、感じることができた
自然の力。
恥ずかしながら、それまでは
ほとんど意識することはありませんでした。
それは
僕の心、生き方に問題があったのです。
自然の力は
意地張った心、頑な心では
感じることができないのです。
素直な心になってはじめて
自然の力を感じ、受け入れることができるのです。
素直に自然の力を受け入れることができれば
いつでも、どんな時でも
自然の力は、あなたを、僕を
喜んで守ってくれるのです。
自然の力は
前回お話をした神の経、神経を通して
60兆個の細胞一つ一つに伝わっていきます。
素直な心がないと
すべての細胞を司っている神経が
硬直すると言われています。
神経が硬直して働けなくなると
細胞も同様に働けなくなり
体の中に毒素をため込んでしまいます。
それが
病気や不幸を生み出してしまうのです。
神経は
からだを動かしている働きがあると
現代医学では考えていますが
実は
宇宙からの力が
自然界からの力が
僕たちのからだに伝えてくれているのです。
そして
宇宙からの英知を受け取って
僕たちは生きている、生きられているのです。
そのことを
素直に受け入れていきることができれば
病気になることもなく
心豊かに生きていけると思うのです
カテゴリー: 今日の言葉
人は誰かと見守られて生きている はコメントを受け付けていません
日本人の魂
日本人は世界的に見ても
他に類を見ない民族ではないでしょうか?
そのひとつが
宗教に縛られない民族だと言うこと。
日本人の多くは仏教徒だから
死んだら仏様に手を合わせて
家には仏壇でご先祖様をお祀りします。
クリスマスもバレンタインもハロウインモお祝いして
お正月や七五三では神社にお詣り
どんな宗教でも受け入れてきた民族です。
どうして、こうなったのか?
それは神武天皇が日本国を作った時に
「養生」と言うことを発しておられるのです。
これは
何が正しいかを宗教や神の教えなどに固定せず
正邪を見分けるこころを養い、広め
正しい方向に向かっていこうと考えたことに
よる気がするのです。
だから、何が正しいのか、何が必要なのかを
自分自身の心で判断することを
ずっとおこなってきたことによるのでは亡いでしょうか。
我々の魂には
「養生」という想いが根付いてるのです。
大切にしたい日本人のこころです。
カテゴリー: 今日の言葉
日本人の魂 はコメントを受け付けていません