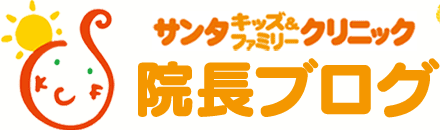検索
カレンダー
-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
リンク
「今日の言葉」カテゴリーアーカイブ
時計の文字盤が円いわけ
時は、真っ直ぐ進む訳じゃないから。
円環のように、ぐるぐる同じ所を回っているから。
そして、人間は
その円環から、決して逃れることはできない。
円環という牢獄の中に
閉じ込められているのかもしれない。
でも、実は
閉じ込められている円環から
人生のなかで
一瞬その円環から解放される時があるという。
それがいつ起こるのか
いつ起こったかもわからないかもしれない。
しかし、その瞬間に
それまでの人生とは大きく異なる
何かが生まれる瞬間を経験するという。
その時は
一瞬のタイミングであるという。
その一瞬のタイミングを確実につかむために
今この一瞬一瞬を生ききることが
大事なのです。
カテゴリー: 今日の言葉
時計の文字盤が円いわけ はコメントを受け付けていません
波動を合わせる
宇宙には
あらゆるエネルギーが充満しており
自然界にあるすべてのものは
宇宙全体とつながっています。
そして人も例外ではなく
全ての人が
宇宙とつながっているのです。
ですから
宇宙全体に波長を合わせることで
大きなエネルギーを受けることが
可能になるのです。
そして
宇宙の波動を合わせることで
自分のもっている波動を
変えることが可能になるのです、
すなわち
医学的に治すことが困難だと
考えられる病気でも
宇宙からのエネルギーを受ければ
治ることも可能だと
考えられます。
これは
病気のことだけでなく
宇宙のエネルギーの波動と
合わせれば
全てのことが
自分の思うままの方向に
動き出すこともできるのです。
でも
そうだと知っていても
現実にはそう動き出すのは
容易なことではありません。
ただ宇宙のエネルギーと
波長を合わせるだけでは足りないのです。
仏教の言葉に
三密加持という言葉があります。
加持の加はというのは
宇宙の力
持というのは
こちら側が受け取る状態であるということ
密は密着しているということ。
すなわち
こころとからだそして魂も合わせて
宇宙からの力を
受け入れる準備ができていることを
表現した言葉なのです。
仏教でも
宇宙からのエネルギーの存在に
合わせて生きていくことの大事さを
教えてくれているのです。
人間は自分ひとりで
生きていない
いえ、生きられるわけではないことを知り
全てのことに感謝して
生きていくことから
全てのことが始まるのです。
カテゴリー: 今日の言葉
波動を合わせる はコメントを受け付けていません
円谷英二監督の予言
円谷英二監督といえば
ウルトラマンやゴジラシリーズなどの
怪獣シリーズを特撮技術を開発し
普及した特撮の父ともいわれる方です。
多くのウルトラマンシリーズに
関わってこられましたが
その数多くあるウルトラマンのなかで
唯一自らメガホンをとったのが
「悪魔はふたたびやってきた」の回だけです。
この回は、どこか異種異様なんです。
怪獣アボラスをオリンピックが行われた
国立競技場で戦わせ、
戦いに勝利したウルトラマンはは
完全に破壊された国立競技場を後にして
宇宙に飛び立て終わるんです。
通常なら
戦いが終わった後
ハヤタ隊員が宇宙警備隊のもとに
笑顔でもどってきて終わるエンディングですが
この回はウルトラマンが去って
あっさり終わるんです。
ほかの回とは異種なエンディング。
これは円谷英二監督の未来に対するメッセージが
込められていたのでは思うのです。
実は当時福島原発を福島に建設されることが決まり
実は福島出身の監督が
原発建設の未来に危惧したのではないだろうか?
もしかしたら
題名の悪魔は原子力発電所。
その悪魔による破壊が再びやってくる
そのことを予言し、危惧した
メッセージっだったように思えるのです。
人間の文明発展には
完全ではなく、大きなリスクもある。
そのことを考えて未来を作っていかないといけないと
思うのです。
カテゴリー: 今日の言葉
円谷英二監督の予言 はコメントを受け付けていません
嫌な体験を未来につなげるために
年が明けると
将来に向けての活動が活発になります。
そのうちのひとつが
受験シーズンでもあり
おとなだけでなく
こともたちにとっても
今までにない
不安な気持ちを抱き
日々嫌な気持ちが湧き上がって
来てしまう中
人々は必死に生活されていることでしょう。
どんな嫌なことを体験したとしても
学ぶべきことはあります。
その嫌な体験を
嫌なことだと思うだけで
学ばないままにしてしまうと
いつまでもその体験は
嫌な思い出として
今後の人生に尾を引いてしまいます。
ですから
嫌な出来事が起こった場合
「決して無駄な経験ではない。
何科学ぶべきことがあるはずだ」と
思い直してみて下さい。
嫌なこと、体験を逃げずに
様々な立場で
その思いを体験を
眺めてみて下さい。
そして
こんな思いを二度としないですむ
生き方をしていこうと
決意しましょう。
その時
こころに留めていただきたいのは
自分にとって大事なのは
過去でなく
今をどう生きるかということです。
過去は今後につながる
土台となるものです。
全ての過去の経験が積み重なっていくことで
強固な石垣となり
その上に自分の城が築けるのです。
カテゴリー: 今日の言葉
嫌な体験を未来につなげるために はコメントを受け付けていません
文明の利器
脳出血になって
歩けない時期
それどころか
立ち上がることすらできなくなり
それでも
リハビリのおかげで
今では
自分で立つことも
自力で歩くこともできる。
入院した時の
医師、看護師、そしてリハビリ師さんの
おかげだと
今もそしてこれからみ
そのご恩は忘れることはできません。
生活することには
全く不自由はないのですが
正直な話
発病前と全く同じ状況では
ありません。
歩くスピードは
発病前の80%ってとこで
走ることはできません。
持久力も
以前はどんな山道でも
どんどん歩くだけの脚力はありました。
しかし今は
道なき道を歩くのは
大きな冒険であり
正直躊躇します。
でも、先ほどお話ししたように
僕の自由は
病気によって奪われることはなく
自由な生活を取り戻しています。
自由な生活ができるのは
文明の利器の
恩恵のおかげなんですね。
行きたいことがあれば
自分で歩かなくても
車を運転すれば
どこにでもいける
欲しいものがあれば
インターネット経由で
全国いや全世界から
取り寄せることだってできる。
会いたい人がいても
連絡手段には事欠かない。
本当に
有り難い時代にいるから
僕は生きていけるのだと思う。
そして
今、この時いられるのは
周りの方々のやさしさ、思いやり、気遣い
のおかげ。
ものにも人にも感謝の気持ちでいっぱいです。
人は
ひとりで生きているわけではない。
ひとりで生きていけるわけではない。
だから
全ての人にものにそして出来事に
感謝なんです。
カテゴリー: 今日の言葉
文明の利器 はコメントを受け付けていません
AIが考えるしあわせの方法
今巷で流行っているAIに
「しあわせを感じるためには
どうしたらいいですか?」ときいてみた。
すると次の五つのことが大事だという
答えが返ってきた。
①他人との繋がりを大切にする
②自分の価値を認める
③感謝の気持ちを持つ
④前向きな考えをもつ
⑤こころとからだを健康に保つ
そして最後に
「しあわせは
努力次第で手に入れることができるものです。
これらの方法を参考に
是非しあわせを感じられる自分を目指して見て下さい」
と粋なコメントが添えられてあった。
AIは生きてる人のように
そして
答えだけでなく
その先にこころを揺らがされるコメントが
返ってくるのが
AIが人の心を捉える理由なのでしょう。
僕は
生身の人間として
AIに負けないように
寄り添い、こころを届けようと思います。
カテゴリー: 今日の言葉
AIが考えるしあわせの方法 はコメントを受け付けていません
美しい言葉を
人間が発する言葉は
「言魂」と言って
口から発する言葉そのものにも
魂があり、言葉のもっているエネルギーが
その言葉を聞いた人の魂の奥まで届苦こともあり
そのひとことで
いのちそのものも
活性化することもあれば
奪ってしまうことさえあるのです。
「覆水盆に返らず」という
言葉が示すように
一度相手の向けられた言葉を
再び取り返すことはできません。
ですから
「的確にかつ素直に相手のことを思って」
「こころを和らげる言葉を選んで」
などを心がけて
日頃から言葉を発することが
大事です。
心地よい言葉を使っていると
こころもからだも
うれしく良い方向に進んでいきます。
こころとからだは
言葉に影響されるのです。
以上のことを思って
日頃から言葉を使ってると
他の人の発する言葉が
神様や仏様の言葉と思えるように
素直にきけることでしょう。
「行動、言動は習慣を作り
習慣は人格を作り
人格は運命を作る」というように
「いつも感謝のこころを持ち
感謝の言葉を素直にいつも発する」
ここから
心地よい人生が紡いでいくのだと思います。
カテゴリー: 今日の言葉
美しい言葉を はコメントを受け付けていません
夢の役割
最近よく耳にする言葉
思いは現実化する。
確かにそのとおりなのだけど
思いはいい思いばかりではない。
怖れる気持ちなど
不安なき持ちをもっても
そのことが現実化してしまうのも
マイナスの思いも現実化するのも
真実だと思う
でも、マイナスな思いを
解消してくれようとする働きが
人間には備わっているのです。
その働きをしているのが
夢の働きなのです。
夢を視るのは
怖れるこころ、不安なこころなど
マイナスのこころを解消しようとする
働きがあるのです。
夢は
人の業や因縁を
消し去るために視ているのです。
夢を見ることで
思いを一度夢の中で体験し
業・因縁を断ち切るために
我々は夢を見ているのです。
昔から
初夢でその年を占う
風習があります。
いい年にしたいから
いい一年になることを願い
縁起のいい夢をみようと
努力?して布団に入ってました。
確かに
夢には楽しい夢をみることも
しあわせな夢をみることも
あるでしょう。
みた夢が
しあわせな夢であってもなくても
夢をみることで
思いを疑似体験しているのです。
その思いが現実化することが
どのような意味を持つのかを
知るためなんです。
でも
夢をみても
目覚めると
覚えてないことがほとんど。
夢が思い出せないのは
夢が思いを戯画化されたもので
肉体的に感じても
魂に記録されるような
本当な体験にはならないからなんです。
夢は
その人の思いの現れ。
言えることは
どんな思いをもってるかが大事。
必要な思いは
必ず現実になるということ。
今日は共通テスト。
本格的な受験シーズン到来。
自分の思い、
その思いと向き合って来たことは
必ず叶うのです。
だから
自分を信じて
夢に向かって
頑張れ、受験生!
カテゴリー: 今日の言葉
夢の役割 はコメントを受け付けていません
三流をめざす
年頭に当たり
今年はこうなろうと
目標を持たれるかたも
多いことでしょう。
僕は
今まで少しでも
一流の仕事をしようと思い
実際実践してきました。
でも
今年は3流を目指そうと思います。
なぜ、三流を目指すのか?
楽をしたいからなの?
ちょっとがっかりだという声も
聞こえてきそうですが
実は
一流、二流、三流について
こんな話を聞いたからです。
一流の人はひとつの道を究めた専門家
二流の人は二つのことに詳しい専門家
三流の人はいくつも専門をもつ人
つまり
いくつも専門をもつ三流の人の特徴は
まず、飽きっぽい
そして、好奇心は旺盛で行動力がある。
さらに、興味を持ったら没頭するけど
しかし途中で飽きてしまうから
なかなか究めない。
そして
次の目標を見つけ
転職したり
新しいことをゼロからはじめたくなり
新しい道を踏み出す勇気を持ち合わせている。
また一流の人と一番違うのは
挫折、逆境に強いということでしょうか。
一流の人は
これを成し遂げるという
大きな目標を掲げ、それにむかって
突き進んで行きますが
挫折を覚えると
ショックは大きく
立ち直るのは容易ではありません。
一方
三流の人は
「目標」に対する思いが一流の人より弱いところがあり
ある意味目標に対して柔軟に対応でき
軌道修正も容易にできる。
それは
一流の人は
未来を起点に今を生きているが
三流の人は
未来でなく「今」を起点に生きている。
今の自分が今をしっかり生きていることが
大事なので
傍から見ると
何をしてるのか理解されず
他の人から評価されない人生かもしれない。
しかし
認められることが目標ではなく
今を悔いなく生きることが三流の特徴なので
他人の評価を行動の原動力ではない。
今を精一杯生きて
今できることをこころを込めてやる。
今、この瞬間を
自分のため、そしてあなたのために
生きていく
そんな真の三流を目指して
いこうと決意した年始めでした。
カテゴリー: 今日の言葉
三流をめざす はコメントを受け付けていません
今日の決意は昨日から始まっている
ダイエットしようと決めたたり
何か始めようと決めた時には
「昨日から」がお勧めです。
なぜ「昨日から?」なのでしょう。
それは
行動を起こすには
もうできている、行動している自分で
始めた方が持続するからなんです。
例えば
お酒をやめようと思っていた時
昨日はビールを2杯飲んでしまったいた。
昨日は2杯でも
飲もうと思えば3杯でも、4杯でも飲めたことでしょう。
それを昨日は2杯で納めた自分をほめることから
始めると
目標達成することの近道になるのです。
ですから
決めたことは
昨日のことを振り返り
できたことをほめることから始めると
きっと目標達成に近づくことでしょう。
カテゴリー: 今日の言葉
今日の決意は昨日から始まっている はコメントを受け付けていません