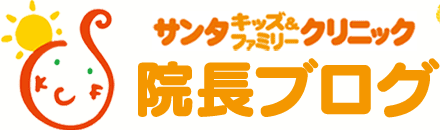「今日の言葉」カテゴリーアーカイブ
ナンバーワンになる確率は?
冬季オリンピックが終わり
連日の熱戦に釘付けの方も多く
まだその興奮冷めやらない方も多かったことでしょう。
オリンピックといえば
誰が金メダルをとるかが
皆の最大関心事項になります。
関心なのは
オリンピックにでるのも大変なのに
ただひとりだけが
その頂点に手にできる金メダルを取るか。
金メダルを採れるのは
実力はもちろんだけど
運の力も大きく働く。
金メダルをとる確率って
どのくらいだろう。
オリンピックの金メダルの数は
およそ300といわれている。
団体競技だったり、
ひとりで複数手にする猛者もいるけど
金メダリストと金メダルの数を同じと考え
世界人口80億人だと考えると
金メダルを手にする確率は
およそ3,5億分の1という
すごい確率。
夢の夢だな・・・と思ってしまう
やっぱり金メダリストは
強運の持ち主だと言える。
金メダリストもすごいけど
実は僕も強運の持ち主なのだ。
僕だけでなく、あなたもみんな強運の持ち主。
僕たちが
この世に生まれるためには
精子と卵子の過酷な生存競争に打ち勝ったきた
結果なのです。
1回の射精で放出される精子は
2~3億個ともいわれ
卵子に最初にたどり着けるのは
1回のチャンスしかなく
卵子に無事たどり着けても
受精までいくのはまた確率が下がる、
ですから
受精にまで至るには
3億分の1よりも低い確率になります。
また卵子は180万個あるけど
女性が生涯排卵する卵子は500個
ともいわれ
卵子が異なれば
今のあなたと別人格になってしまう。
あなたの今を形作った精子と卵子が出会い
今の僕やあなたが誕生した確率は
文字通り気の遠くなる
天文学的な確率で
勝ち抜いて存在するのです。
そう考えると
この世に生まれていることが
強運なのだ。
こんな僕でも
神様の祝福があって生まれてきたのだから
このいのちを大事に
そしていのち輝かせて生きていける
はずなんだと思うのです
地獄があるのは?
死んだ後どうなるかは
どんな偉人も実際に経験した人は
いないといわれている。
しかし、世界中の宗教では
死後の世界には天国と地獄があり
死んだ後
どのように生きてきたかの審判を受けると説く。
実際にあるかどうかわからない
地獄に対して
全宗教が説いているのには
それなりの意味があると思うのです。
まず
死後の世界で審判があると信じていると
生の世界で善行を積もうという動機が生まれます。
そして、精一杯善行を積んで生きていると
死に対する不安が軽減されていきます。
そして、もし過酷な状況に生きたとしても
善く生きれば、しあわせな世界がまっていると
生きている時の絶望の状況から
救出してくれることになります。
このように
地獄があると思うと
より正しく生きていくことができるのです。
関係を育てる
こどもの時
植物でも、動物でも
何か自分で育てた経験って
おとなになった時
人間関係を気づく時に
役に立つんだと思う。
友達との関係も
誰かを好きになった時も
人との関係は作るものではなく
育てるものだと思うから。
仲良くなりたくて
勇気をだして一歩を踏み出し
仲良くなった後
いつもいい関係ばかりじゃない。
時には壊れそうになったり
傷ついたり、傷つけたり
でも
また元の状態になれるように努力して
お互いの関係が深まっていく。
その時に大事にして欲しいのが
”育てる”という愛情。
関係を育てるって
”こうすればいいよ”
”そんなことしたらだめだよ”と
自分の考えで
口を挟むことじゃなくて
自分の意見じゃなくて
相手の気持ちになること
だと思う。
”あなたは今どうしたいの?”
”何に困ってるの”
”どんなことに喜びを感じるの?”
”どうされると嫌なの”
相手の立場で
考えよう、答えを見つける努力することで
関係は育っていく。
でも、その答えを
いつも帰ってくるとは限らない。
人は、動物や植物と違って
話すこともできる
聞くこともできるのに
知らないうちに
相手の言葉に耳を傾けていなかったり
自分の思いだけを話したりする。
その時に
こどもの時育てた
何もしゃべらなかった花のこと
何も教えてくれなかった動物のこと
を思いだしてほしい。
あなたの可愛がってる
花を動物のことを
少しでもわかってあげたいと
目、耳、鼻、全身を使って
観察したと思う。
そして
自分なら・・・って考えたと思う。
五感をすべて使い
想像力を駆使して
あなたとその人との
”関係”を育ててほしい。
そうすれば
美しい花が咲くはずだから。
キーワード
今日は今生きている自分というものを
自己紹介形式で3つのキーワードに絞って
書いてみようと思います。
僕は池内克彦と申します。
職業は医師。
赤ちゃんやこどもの命を守る小児科専門医として
こどものこ家族の健康を守る家庭医として日々働いています。
小児科医の仕事を一言で言えば、
自分で意思表示の出来ないこどもの命を守ることです。
だからみなさんに大変だねって言われます。
そこで今日は
どうして自分が医師それも小児科医になったのか?を
3つのキーワードに沿ってお話しします。
第一番目は“笑顔”。
笑ってないこども、困ってる人やしあわせでない人を見ると、
なぜ?どうして?笑わないの?体の具合が悪いの?
笑顔でない人をほっとけないのです。
いつも笑顔でいてもらいたいのです。
第二番目は“愛”です。
親がこどもを愛する、人が人を愛する。
愛情を注いでいるものに対して、
僕もその愛を全力で応援して支えてあげたいのです、
愛を守り、愛を大事にしたいのです。
そして
最後は“信頼”。
自分を信頼してくれるのなら、
その人を全身全霊込めて守りたい
という気持ちが起こります。
あなたに信じてもらえたら
僕はどんな時も頑張れるんだと思います。
“僕を信んじて、
頼ってくれる人が笑顔でいるために、
全身全霊愛をもって生きていく。”
それが
僕が今医師たる理由なのかもしれません。
そして、
これからも多くの人が、
今よりも
しあわせで愛あふれる豊かな人生を送れるように
日々医師として信頼と愛を持って生きていくのだと思います。
あなたにとってのキーワードっては何ですか?
神の御業~「神曲」を読んで~
川村元気作「神曲」を読んだ。
どんな作家かも知らず
どこか題名に惹かれて
手にした。
内容は
こどもが通り魔殺人事件の被害に会い
家族が苦悩するなか
新興宗教に家族でのめり込んで
宗教にすがる内に
人間の愛や悲哀に気づくという話。
この本で
予期せず神(宗教)にはまり込んでいく
その心理を学ばさせていただいた。
この小説の中に
神のような大きな力について語った
こんな一節があった。
この世の花びらの数は
3.5.5.13.21,34,55、89・・・・
という法則がある。
これは1,2番目の数を足すと3番目の数になる。
2,3番目の数を足すと4番目の数になるという
規則性があるというのです。
この自然の法則を
決めたのは人間ではない
自然界を支配する大きな力
これが神の御業だと思ってしまう。
みのまわりには
科学では解明できない
まさに神の御業としか考えられない
ことが確かに存在する。
実は宇宙の95%は
まだ解明されていない
未知の物質やエネルギーでできているそうだ。
科学が進歩しても
我々人間が把握できるのは5%。
この世の中は
人間の力の到底及ばない力
すなわち神の御業があることで
生きていくことができている、
神の力は
この目で見ることはできない。
音は聞こえないけど
確かにそこにあるものがある。
この世界から失われたものも
じつは永遠という世界には
きちんと存在している。
人々は
目に見えない
人智が及ばない世界にも
目を耳を意識を向けないといけない。
ハーモニーが心地よく感じた時は
神が創造した宇宙と人間の意識が
調和したから。
確かに神の世界はあるということを
僕たちに訴えてきた一冊でした。
☆今日は一粒万倍日です。
その日まいた種が一万倍にもなって実る日です。
いいことだけでなく、悪いこともなんです。
今日はいいことを心掛けて過ごしましょう
「わたしたちはよき祖先になれるか」
これはポリオワクチンを開発した
イギリスのウイルス学者ジョナス・ソーク氏の言葉。
彼はポリオワクチンを開発に成功して
このワクチンは発展途上国のこどもたちにまで
しっかり行き渡り
全世界の小児麻痺の98%は焼失した。
このように
ソーク氏の偉大さは
ポリオワクチンを開発したこともおおきいが
彼は、ワクチンを開発した後名声や富に
関心を示さず、ワクチンの特許を放棄したのです。
それによって、こどもたちは救われたのです。
ソーク氏がこのような行動にでたのは
「我々が先人から多くの恩恵をうけているように
我々も未来世代に多くの恩恵を
渡さなければならない」といううのが
彼の信条だったからのようだ。
そして
こどもや孫そして子孫のために
きっといい先祖になることを目指して
いたのだと思う。
彼のいい先祖とは
偉大な業績を残すだけではない。
今存在する苦悩を乗り越えるために
今あるものを作り直し
未来に生きる世代に
夢を与えることを目指していく
夢を繋いで逝くことだったんだと思う。
私は私でない私である
この言葉は台湾の元総統李登輝氏が残した言葉。
「我是不是我的」日本語に直すと
「私が私でない私である」ということになるのですが
ちょっと意味がわかりにくいです。
ちょっと説明すると
自分という人間は、立場によって
色んな役割があります。
家庭では、父親であり、夫であり
社会では医者であり、院長であり
と色んな立場で暮らしています。
その立場の目的は
家庭が、特にこどもが
人として一人前に育ち、社会の役に立つ人間に
なるように育てる。
クリニックが、社会の病気で困った人の
役に立てるように働く場にする。
と言うことですが
李氏が、それだけでいいですか?と
問いかけているような気がするのです。
つまり
あなたは私人としての立場で
考えて生きていますが
あなたは家庭の外にある社会つまり公のために
何をしているのですか?と
問いかけている気がするのです。
この言葉を見て
ハッと気づかされました。
現代の日本に生きる自分たちは
ひとりひとりを大事にする社会になったけど
個人だけがよくなればいいのでしょうか?
まず自分がしあわせになることばかり
考えていないだろうか?
そう言えば
親世代が家の前を掃除する時
誰が見ているとかに関係なく
右隣りも左隣りも掃除していなかっただろうか?
どうせしているから、一緒にしておこうという
気持ちが自然に起こっていたと思います。
最近あまり聞かれなくなった日本語に
「向こう三軒両隣り」という言葉があります。
これは自分のとこばかりしないで
周りのことにも気を回しましょう
という言葉です。
でも、最近はこの言葉のいう意味が
失われてきている気がします。
日本教育で育った李元総統も
にほんじが元々持っていた
公を大事にする気持ちを失ってきていると
語っているのです。
公つまり社会のことも考えて
行動していく社会にしていくことが
今を生きている日本人の役目だと思うのです。
過去の時間は全て今の中にある
過去は、すべて今の中にある。
その証拠が星空なんです。
星から届く光は「今」の
光じゃないのです。
今からずっと昔
その星から地球に光が届くまでの年数。
たとえば、光が届くまでに7年かかれば
地球でみている、星の光は
7年前の光ということになる。
この地球に届く光は
百年前の光、五百年前のひかりなど
様々な時間の光がこの地球にあるということ。
つまり過去のすべての時間が
今この宇宙には存在しているということ。
そして、タイミングを捉えれば
人は時間の円環から自由になれるのかもしれない。
僕が生まれた時が
今、この宇宙に存在している。
時間から自由になれるタイミングがあるはず。
そのタイミングを捉えるのは
偶然ではなく必然のことのような気がする。
これは宇宙の法則なんだよ。と
瞬く星たちが教えてくれた。
心感じるままに
若い時は
いろんなことを学びます。
学んでるときは
「真実とは?」{正しいこととは?」などに
目がいってしまいます。
そして、
なんのために勉強しているのか
わからなくなってしまうこともあります。
実は勉強し学びを深めることも大事だけど
実は
学んでる時でも
何をする時でも、
その時の感じる心が大事。
”勉強して、わかって楽しくなった”
”今日、頑張って走れたことがうれしい”
”そうじをすると、心がすっきりした”
”お友達と仲良くできて、心が明るくなった”
とか
心で感じたことを
大事にしてもらいたい。
心に感じたことを
大切にして
日々暮らしていくと
”自分は今、何をしているとうれしいのか
自分は今、何をしている時が充実してるのか”
考えるようになります。
そんな風に生活していると
何かに悩んだ時でも
その心の中に
自分らしく生きるヒントを
見つけることができます。
しあわせになる鍵は
自分の心の中にあるのだと思います。
将来
何をしたらいいかわからなくなった時
なぜ、勉強しているのか
わからなくなった時は
自分の心に質問してみて下さい。
”今、何をしたら楽しい?”
いつも
どんな時も
頭で考えたことより
心で感じることを大切に
生きてもらいたいです
みなさんにとってもいい一日になりますように。
清く、明るく、美しく
世の中は受験シーズン到来と
春を前に
どこか不安を多く感じ
社会的にも
医師が襲われたり
未成年が暴行されたりと
悲惨なニュースが連日伝えられます。
殺伐した世の中の流れを感じますが
こんな時だからこそ
今生きている世界の本質を忘れては
いけないと思うのです。
「この世の中は、
苦しいものでも悩むべきものでもない。
この世界は
本格的に楽しい、うれしい
そして調和した美しい
花園のような世界である」よいうこと。
でも
実際に感じるのは
花園とはほど遠い
ゆがんだ、曲がった世界ではないでしょうか?
ゆがんだ世界にしているのは
ものにあふれ
情報にあふれ
惑わすものに囲まれた
現代社会のなれのはてなのでしょう。
この曲がった世界にいるので
からだが病み、こころが病む人が増えたのでしょう。
そのためには
あなたのこころを惑わすものを感じたら
「さらり」とかわし
するりするりと後へ残さないようにして
生きていくのです。
そして
ひとつ覚えていて欲しいのは
あなたのこころは
「清く明るく美しい」ものだということです