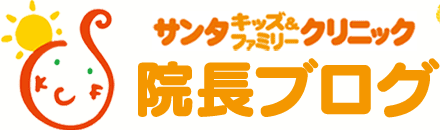「宗教」という言葉は
幕末に「Religion」の翻訳後として
つくられた言葉だと言われています。
それまでは宗教という言葉はなく
仏教であれば「宗門」「宗派」
神道であれば「かんながらの道」と
読んでいたのです。
ヨーロッパなどの外国の宗教は
イエス、マホメット等の開祖が伝える教えを
総じていうものなのです。
ですから、宗教は「教え」でもありますが
それに対して
日本人の日本固有の宗教に対しては
教本などはなく
教えと言うよりも
より良く生きるための「道」を
示してます。
この点が西洋の「宗教」とは
大きく異なる点です。
西洋の宗教では
特定の神を信じ
その教えに従うことで救済を得ると考え
日本では
「神になるための道」として存在し
そのために仏教や儒教、さらにはキリスト教がある。
もっと言えば
日本人は、いい教えであれば
どんなものでも学ぼうとする
柔軟性を持っているのです。
ですから
クリスマスもお祝いし、
お盆やお彼岸ではお寺に行き
節分には豆まきをするのです。