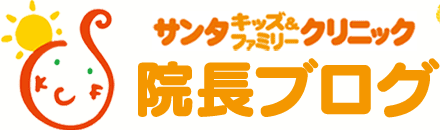「子育て」カテゴリーアーカイブ
くつろいだ暮らしの時間
健診などで
まだ生まれて間もないお母さんが来られると
出産という大事業を終え
疲れを癒やす間もなく
ぐっすり眠る時間もうばわれる
3時間ごとの授乳。
きっと大変だろうと思い
お母さん方に思わず
労いの言葉をかけるのですが
当のお母さん方は
「大丈夫ですよ」と笑顔で答えられる。
その笑顔には
偽りの苦笑いではなく
しあわせいっぱいの笑顔に見える。
男性にはわからない
母の授乳の時何をかんがえているのだろう?
歌手の加藤登紀子さんが
次のように語っている。
出産を終えて、自宅で過ごしている時に
語った言葉です。
「一生のうちで一番くつろいだ暮らしかも
しれない毎日です。
夜中に起きてお乳を飲ませることも
さほど苦しいことではなく、
赤ん坊と一緒に眠り、
一緒にお乳を飲む時間を慈しむという
何のこだわりのない繰り返しです。
もちろん、わけのわからない時に
ぐずぐず泣いたり、抱き上げればもう
すっかり安心しきって
うっとりしていたり
駆け引きを心得ているがごときです。
細くて、小さな手で空をさぐり
とてもいろんな可愛い表情をします。
お乳を飲む時は
しっかり、乳房をのがすまいとする風だし
うまくいかないち、きーとひっかいたりします。
お乳を飲んだあとは、
うっとりして、y時にはもう笑います」
と書いています。
母親にとって
授乳時はその時にしか味わえない
しあわせな時なのでしょう。
そう言えば
自分の母親が
一生懸命おっぱいを飲んでいた自分の様子を語り
可愛かったと話していた言葉を
今も思い出します。
母親の愛に感謝です。
そして
赤ちゃんとの出会いの時間を
大切に過ごしてもらいたいと思います。
母親はなぜ強いのか?
どんな女性も
こどもを産むと強くなると言われます。
それは
こどもを守るとする
母性が働くから・・・と
わかったような理由がよく聞かれます。
なぜ、強くなるのかは
出産を経験した女性にきくのが一番。
歌手の加藤登紀子さんが
出産を間近に控えて次のようなことを述べています。
「女は、子供を産んで強くなるというけれど
多分、きっと、赤ちゃんを産んだその時に、一度、
死ぬだろうと思います。
親が悪戦苦闘して
こどもを育てる頑張りの図が目に浮かぶけれど
ほんとうは、自然の摂理にいったいとなって
母のからだは、透明になってしまうのではないかと
思うのです。
その時、母は、
旅するこどもの日影しかない。
そしていつか子供は
母の影の存在にかかわりなく
一人で歩いていってしまう。
女は、こうして、生き死にをくり返していくのでしょう」
と書き残しています。
なるほど
女性が母親となり
母親に育まれたこどもが一人で歩んでいく
女性は、赤ちゃんを産んだその時に
それまでの人生と決別、つまり死ぬのです。
現代版”知らない人について行ってはいけない”
僕たちがこどもの時には
親や先生から
「知らない人について行ってはいけません」
とよく注意されました。
もちろん現代でも
誘拐事件がないわけではないので
もちろん
事件に巻き込まれないためにも
知らない人について行ってはいけないのですが
これに加えて
こどもたちに伝えたいのは
「知らない人の言葉を気にするな」と言いたい。
昭和の時代と比べて
現代はSNSが発達して
ネット社会では知り合、知り合いにかかわらず
誹謗中傷する言葉にあふれている。
自分に関係ないとわかっていても
攻撃な言葉に触れると
気持ちいいものではないし
もし、自分についてであるなら
どんなに傷ついてしまうだろう。
匿名性ではなく
本人に直接言うべきだし
いちいちネットの言葉に左右されることは
決していいことではない。
最近あまり聞かれなくなった言葉
「影でこそこそ言うな」
「知らない人の言葉に左右されるな」
という言葉を付け加えたい。
言葉を話せないだけで思いはいっぱいある
みぞろぎ梨穂さんという詩人がいる。
この女性は
普通の女性と言うだけでなく
この女性は生まれてすぐ低酸素によって
一生寝たきりの最重度脳障害の女性なんです。
自分で食事もできない
しゃべることもできなかった彼女が
どうして詩人になれたかというと・・・
國學院大學で障害児教育を研究されている
柴田保之先生との出会いによるものです。
柴田先生は
障害の重いこどもの中に存在する
「内的な言語の存在」に気づかれ
梨穂さんの内面にある言葉を
引き出してくれたのです。
柴田先生に引き出された詩のひとつを詩を紹介します。
「私の未来はどんな未来だろう
私はひたすら生きる意味を探して
今を生きる
本来の私は
どこで終わるかわからない
けれど終わりの日が来ても
悔いを残さないように
楽しく今を生きる
私の人生は大変なことばかりだった
苦しいこと何回もあった
だけど今はとても幸せ
私を理解してくれる人は増えたし
私の声を聞いてくれる人は増えたし
私の声を聞いてくれる人も
多くなってきた
そんな時代に生まれてきた私は
幸せかもしれない。
今はまだ生まれてきた意味は
曖昧だけれども
いつか必ず見つけてみせる」
この詩を読んで
障害者といわれる人にも
いっぱい言いたいことがある。
僕も小児科医として
そのこどもたちの声を感じて
診療していかないと行けないと強く思った。
増えるこどもの自殺を救うには
朝日新聞の社説に
「こどもの自殺、女子急増の背景に目を」(20251028)
の記事が載っていた
厚生労働省の「自殺対策白書」によると
昨年は小中高生529人が亡くなり、
過去最多だったというのです。
特に
2020年頃から特に女子高校生の自殺が増えており
過去5年に比べて倍近くに増えているのです。
自殺の背景のひとつに
SNSの普及が若い女性の心の健康に及ぼす
影響が大きいのだと思います。
もう一つは
市販薬の乱用、最近注目されている
オーバードーズの広がりもあると言われている。
何事にもいい面と悪い面があります。
ネット空間は
匿名の状態で繋がりがもてるので
救われるという人もいるけど
どんどん孤独の闇に引き込まれて
八方塞がりに陥ってしまうことも。
そして
市販薬に対しても
使い方によっては
乱用することによって
思わぬ落とし穴に落ちてしまうことも原因だと思う。
どちらも
多感なこども時代に感じる
孤独感が根本にあると思う。
親をはじめ
周りのおとなはこどもたちの味方に
なりたいと思っているはず。
こどもの世界は複雑で重層的。
学校、家庭、塾や習い事、そしてネット空間
どこに安らぎの世界を求めているのか
そのことに気づき
まずは温かく見守っていくしかない。
そして
いつでもSOSの時に手を差し伸べる存在として
おとなはいるのが一番。
ぼくも小児科医として
こどもたちが困った時に
いつでもノックしてもらえるように
こころの扉を開けている存在でいたいと思う。
大事なこどもの遊び
近頃のこどもたちは忙しい。
かつては学校から帰ったら
昔は宿題したら、遊びに行っていたけど
今のこどもたちは
宿題済めばいいというわけではなく
塾や習い事が合って自由時間は少ない。
友達と遊ぶ時間も合わないし
遊ぶ場所もないし
だから、一人でゲームで遊ぶ時間が
増えたのではないのでしょうか?
遊ばなくなったこどもたちには
こどものうちに遊ぶ時間を
もっととって欲しいと思います。
というのは
遊びは、相手の力を見極めながら
ルールを作りを考えていきます。
つまり、相手の体力や気分などを
推し量らないと
一緒に遊べなくなります。
だから
遊びを通して
相手を思いやる感性や
一緒に過ごすためのルール作りを
学んでいるのです。
そして
ルール作りが上手くいくと
その遊びは楽しくなって
こどもたちの笑い声が響く笑いになるのです。
大きな声で笑うと、気持ちもスッキリ
友情や、もっと楽しく生きていこうという
前向きな気持ちも生まれます。
こどもの遊部ことは大事なこと。
こどもたちに是非遊ぶ時間と遊ぶ場所を
提供するのがおとなの役目なのかもしれない。
”食べ物”を食べる
病院にかかったり
からだを壊すと
からだにいいものを食べましょう…
と言われますよね
食べ物があふれている
健康ブームの昨今
からだにいいと言われる食べ物が
現れては、消えて・・・・
からだにいい食べ物ってなんだろう?って
何をたべたらいいのか悩みませんか
食べ物を選ぶ時に
大事なことは
“食べ物を食べる”ってこと。
食べ物を食べる????
人間以外の野生の動物は
何を食べていますか?
ライオンなどの肉食動物は
獲物をとってすぐ食べ
シマウマなどの草食動物は
自然に生えている草を食べてますよね
時間が経っても
腐らないもの
時間の経った
動物の死骸
枯れかけた草は
普通は食べません
そう
野生の動物は
“生き物”しか
食べないのです。
“生き物”って
死んでしまうと腐ってしまうもの
添加物を使った食べ物
加工品のような
腐らない食べ物は
実は“食べ物”ではないのかも
ドッグフードを食べている
ペットは
人間と同じ病気に苦しんでいます
だから
人間も
添加物が多く含まれた
腐らないものを
食べたら
健康でいられないのです
自然にある“生き物”を
そのまま丸ごと
食べるのがいい
お米なら
精米された白米より
胚芽のついた丸ごとのお米“玄米”がいい
マグロの刺身より
小魚を丸ごと食べたほうがいい。
“生き物”には
生きる力がみなぎっているんです。
胚芽のないお米は、
もう稲になることはできません。
刺身も
もう海を泳ぐことができないんです。
僕達は
“命の元を慎んでいただいている”
“生き物”から
生きる力をいただいて
いのちのもとをつないで
活かしてもらってるんですね。
“食べ物”を
有難くいただくことが
健康的な食事ですね
「広がる体験格差」人生談で興味の扉を
10月13日大阪関西万博が閉幕した。
開幕するまでは
今我が国で万博を開催する意義があるのか?など
開催そのものに反対の意見も
多かったように思います。
ただ終わってみると
会期184日で2500万人の入場者があり
黒字になり
毎日大行列の報道ばかりで
大成功という感じの閉幕でした。
みなさんは行かれましたか?
僕は残念ながらいけなかったです。
大屋根リンクの映像をみて凄いと思っても
目玉がわからなくて
食指が動かなかったのも
行かなかった正直な感想です。
そんな時
新聞で「広がる体験格差」という記事が目に入りました。
こどもたちは
旅行にいったり、塾に行ったりする
体験の格差が広がっていて
学校ではどこに行ってきたかという
話題はしないようになってきているという
記事が目につきました。
確かに
こどもの頃
よく家族旅行に行っている友達の
話しを聞くことがあっても
自分とは違う風に達観して聞いていたし
数年に一回旅行した時や
サマーキャンプに参加した時など
日常とは違う胸躍る体験したことは
いまでもはっきり自分の心に刻み込まれています。
そして
それと同じように
思い出されるのが
父や母の自分のこどもの時の話し
どんな暮らしをしていたかどうか
聞くだけでもこころに刻み込まれた思い出になっています。
実際に体験するのもいいけど
夜、夕食後ゆったりとした時間に
こどもたちと自分の体験談を語ることも
立派な体験になるのだと思う。
そんな時間を創ることが
お金かけずにできる大事だと思うのです。
才能を伸ばす考え方
秋は、学校では様々な行事があります。
勉強だけでなく、多くのことに取り組むことで
こどもの中に秘めていた才能が
開花してくれればと願うばかりです。
だから多くのことを体験してもらいたいと思います。
その時体験したことを
どう取り組んだかという思考パターンで
その後の行動が大きく変わってきます。
一つ目の思考パターンは「成長マインドセット」。
これは「能力は経験や努力を通じて向上される」という
考え方。これが身につくと、何事にも失敗を怖れず
挑戦できるようになります。
逆に「能力は才能によって決まる」という思考パターンだと
失敗を怖れて挑戦できなくなってしまいます。
結果主義がいきすぎるとこの思考パターンに陥りがちです。
順位など目標を掲げることは、悪いわけではありませんが
ただ目先の結果だけでこどもたちを評価するのではなく
努力している過程に注目して信じて見守ることが大切です。
そうすればきっと、こどもは努力すればもっと成長できる
という強い心が芽生えていくのです