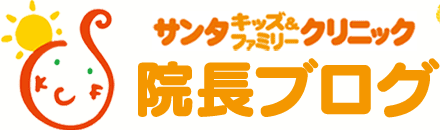「今日の言葉」カテゴリーアーカイブ
こころの持ち方で全てが決まる
こころの持ちようで
今後どんなことが起こるか
運が開くかどうかが決まってくるのです。
人間は弱気になると
不運を招くようにできているのです。
反対に、困難なことが起こったとしても
動揺せずに平気な顔して過ごしていると
悪いこと、不運から立ち去っていくから不思議です。
全てのことは
こころの持ち方で決まるのです。
やるべきことをやる(本日臨時休診です)
自分の運を好転させる方法は
今、やるべきことをやること。
人は先のこと、将来のことを考えがち。
そして
考えすぎて何もできなくなってしまう。
起こっていないことを悩んでしまって
今、やるべきことが
おろそかになっていませんか?
あなたの今起こっていないことを心配する余り
不安になって
行動できなくなってしまっていませんか?
人間はこころの持ち方によって
体の働きや力の出方が代わってきます。
それが健康だけでなく
実は運命までも変えてしまうのです。
だから、どんな時にも
こころを積極的に続けなければならないのです。
だから
「今やるべきことをやる」のは
本当に人生がよくなる法則なのです。
宇宙の法則(本日臨時休診です)
ある朝のこと
お散歩していて
空を見上げると
星が空いっぱいに輝いていて
しばし
足を留めて
星空に見いってしまいました。
満天とまでは言えなくても
その星の存在感に
自分は今見える星の一個一個よりも
小さな存在だけど
宇宙の星に囲まれて
星に、いえ宇宙に守られて
生きている気がしてきた。
つまり
宇宙に確かに存在する
宇宙の法則によって守られているんだと
感じたのです。
宇宙の法則はたくさんあるのでしょうが
僕がその時感じた法則は
善因善果、悪因悪果。
つまり善いことが、悪いことが起こるのも
善い原因、悪い原因があると言うこと。
全ての結果は自分が作りしたもの。
そして
善因の積み重ねが魂を浄化させるのです。
そういえば
お釈迦様は
10個の悪因があり、そこから離れるようにと説かれたのを
思い出しました
10の悪因とは
身(からだによるもの):殺生、盗み、邪淫
口(言葉によるもの) :うそをつく、二枚舌、悪口、有害な噂話
意(こころによるもの):貪欲、他者に有害な思想、邪見
と説かれてます。
この中で特に協調されるのは
こころによるもの。
実際にうそをついたり、盗んだりしなくても
人を傷つけるようなことを思うだけでも
行動したと同じことだと言うことです。
思いは叶う・・・とも言われますが
よいことだけでなく
悪いことの原因にもなるってことに
注意していきていかないといけないんですね。
今日も
こころ美しく生きていきましょうと
星々が語ってくれたように感じた
夜明け前でした。
アダムとイブが作られた秘密(9/22、9/24臨時休診です)
前回のブログで
イブがアダムの肋骨から
作られた意味について
書きました。
エデンの園の話は
こどもでもわかりやすい話ですが
読めば読むほど
深い意味を感じで
色々考えさせられます。
アダムとイブという
神は、どうして男性と女性を
作られたのでしょう?
神と同じ人間を
男と女という分離して作ったことで
魂の進化を促そうと
したのかもと考えてしまいます。
それは
男性、女性と同じ人間だけど
考え方など
性質、性格も全く異なリます。
女性は
ハートや直感が主体で生きているので
内面にある
潜在意識に代表される
智慧んお世界のエネルギーを感じやすいのです。
それに対して男性は
女性性のもつハートの力が弱く
そのため
内面に対するよりも
外側の世界に意識が向きやすく
そのため
好奇心旺盛で攻撃性、支配性も
前面に出やすくなりやすい特徴があります。
今までの男性優位の社会では
戦うことが前面に出て
槍、ミサイル、ロケットなどは
男性性を象徴する発明品だと
思います。
今からの時代
多様性に注目するようになりました。
また
自民党総裁選では
女性の総裁候補が出馬したり
これまでの男性中心の世界が
変わりつつあることを予感します。
もういちど
男性性、女性性を復習すると
男性性の攻撃性は
ハートで象徴される愛よりも
頭の知識を優先し、
頭で考えたことこの目で確認できることを
重視したところから生まれます
女性性は
内面重視で
男性性では感じらることが難しい
ハートチャクラのエネルギーが影響する
見えない形で現される
創造性ややさしさが
主だと言えます。
これからの世界は
男性、女性というのではなく
お互いのもっている特性を知り
その特性をそれぞれがいかせる
時代になることを願っている。
それが
神様が男性と女性の
二性をお作りになった
理由のような気がします。
アダムとイブの秘密(9/22、9/24臨時休診です)
なぜ人類はこの地球に生まれたのか?
最初の人類はいるはず
どんな人だったのか?
考えても結論はでませんが
ロマンを感じ
結論は出ないから
想像の世界が広がり
ワクワクします。
聖書には
神様は
地球を作られた後
神様自身に似た
アダムを誕生させ
アダムの肋骨から
イブという女性を作られたことに
なっています。
みなさんもよく知っている
エデンの園での
アダムとイブの話。
とてもわかりやすく書いてあるけど
読み方によっては
様々な解釈もできます。
イブがアダムの肋骨から
生まれた意味を考えてみたいと思います
僕たちは
食事をとらなくても
数週間は生きることができますが
呼吸ができないと
数分生きるのが精一杯。
そんな呼吸を支えている肺は
肋骨に守られ
肋骨の力も借りて生きているのです。
肋骨が亡ければ生きていくことは不可能です。
また空気を吸うことは
宇宙のエネルギーを
物質としてのからだに取り入れるという
意味もあるのです。
すなわち
生命エネルギーを守っているという
ことが言えるでしょう。
生命エネルギーから生まれたから
イブ(女性)は
こどもを産むことができ
新しい命を生み出すことができるのです。
だから
肋骨からできた人は
イブ(生命)とよばれるのです。
このことは
男性、女性の性差にも
あらわれてきます。
男性は
女性と別れたときは
こころにぽっかり穴が開いたようになり
生命力が衰えたように
元気が無くなる。
それに対して女性は
男性と別れてもこころを切り替え
たくましく生きていくと言う話は
よく耳にします。
これは
男性が頭脳中心で生きてるから
過去に囚われやすいという。
それに対して、女性は
男性よりこころと呼吸(生命エネルギー)が
直結していて
過去よりも
「今」を生きているからなのでしょう。
このように
人間が生まれたこと過程の意味にも
意味があることがわかれば
男性と女性のちがいも
理解できることでしょう。
なら、なぜ
神は異なる性質をもった
男と女を作ったのでしょう。
それにも
大きな意味があると思うのです。
その意味については
次のブログで
喜びやしあわせを感じる時
長い人生の中で
いつも苦しい時ばかりではないし
ずっと楽しい時が続くわけではない。
生きていてよかったと思えるのは
喜びを感じることがあるからです。
喜びを感じた時はいろいろある。
友達や恋人と語り合ったり
家族ができて、こどもや孫の成長を感じる時も
喜びだろう。
旅行した時や美味しものを食べたり
日常から解放された瞬間に感じることもあるでしょう。
もっと、細かく考えると
欲しいものが、偶然手に入った
褒められたとか
予期しなかったことに出会った時も
喜びを感じる時でしょう。
プラスなことが起こった時の喜びだけでなく
失敗だと思ったことが回避できたとか
病気が治ったなど
ピンチを乗り越えたことも喜びの瞬間でしょう。
人生には
多くの喜びを見つける瞬間があるのです。
そのささやかな喜びを見つけて生きていきたいですね。
今さえよければいいのか?
今を一生懸命に生きる
今を生きることに集中することが大事だと
思います。
でも
これは、個人的な生き方の問題
先のことばかりに目を向けるのではなく
現在の、足下を固めて先に進めるべきだと思います。
世の中の全体の流れは
「今さえよければいい」
「この場さえよければいい」
「自分さえよければいい」という感じで
視野が極度に狭くなっているのです。
今を生きることに集中すると言うことは
今自分が楽に生きることではない。
今目の前にある
苦しくとも、目の前の自分に大切なものを
やると言うことなのです。
将来のことより
今やるべき課題を逃げずにやり遂げましょう。
与えられた役割で、自分を磨き続ける
世間では
「運がいい」「運が悪い」などといって
運があるなしを気にする人は意外に多い。
だけど
運とは、
勝手に向こうから
運ばれてくる物ではないと思うのです。
ただ、運が運ばれてくる場所や時は
あると思うのです。
運が運ばれてきている場所にいるのに
その場所で
いかに努力するかどうかが大事なのです。
運が運ばれてきた場所で
やるべきことをひとつひとつ
こころをこめてやることで
運がよくなるのです。
逆に
やるべきことをやらないと
運が悪くなってしまいます。
でも、実際には
どこが運が運ばれてくるかは、わかりません。
つまり
いつも
与えられた場所で自分を磨き上げるくせをつけることが
運がよくなるために大事なのです。
思いを叶える方法
今日のブログのタイトルは
思いを叶える方法なんて
とてもストレートなスピリチュアルな
題名にしました。
またまた
そんな方法言う人数多いるけど
どれもそうかな?って
疑ってかかる人もいるでしょう。
でも
今考え方をかえれば
願いが叶うんだと思います。
そんな願い無理無理・・・だと
思ってませんか?
そう考えると
願わないことをこの人は考えているんだと
あなた自身の魂が思い
あなたの人生がその様に動き出すんです。
からだもそうだけど
あなたがこうありたいように
動けるようなあろうと
してくれているんですね。
だから、無理無理だと思わず
こうありたいと
未来のあなたの姿を描いて
過ごしていけば
その様なあなたになるように
あなたのからだも、こころも、魂も
応援してくれるんですよ。
理論物理学者の保江邦夫先生が
最新の著書の中で
未来の姿が決まれば、過去も決まる。
すると
今という時間は
未来の自分のために進んでいる。
というこれまでの
現在、過去、未来という
今まで考えてたいた
時間軸ではなく
過去と未来が決まれば
進む時間が決まっていくという
パッケージ理論を提唱されていた。
確かに
パラレルワールドというように
この世界は
多数の時間軸が存在している。
過去があり、未来という2点が決まれば
時間の軸は一点だけに決まる。
ベクトルのようなものですよね。
未来を描いたときに
そんなことは無理、できないなど
と考えてしまうのは
自分の頭が考えた
頭の常識で考えて
夢を描いた未来の時間を変えてしまうことで
進む道が変わって
夢が叶わない方向に考えたように進んでしまう。
だから
しっかりなりたい自分を描き
その未来の自分を疑わずに進むことで
今が決まるのだと思う。
あなたはどんなあなたになりたいですか?
その思いを大切にしていますか?
その思いがあなたを変えてくれるのです
祈りがあなたを変える
あなたを変える
これまで人類は
人類自身の発展
しあわせのために
そしてたとの共生よりも
自分だけ勝つことを考えて
科学を発展させてきた。
20世紀をふりかえれば
そんな時代だったと言えるでしょう。
でも昨今の
天変地異ともいえそうな
気候変動
コロナウイルスの混乱を考えると
このままでは
いけないんだと、誰もが
感じてきていることでしょう。
医学の世界でも
20世紀は人の能力を
引き出すために全ての遺伝子解析をすすめ
その結果は
予想だにしなかったものでした。
つまり
人の遺伝子は
人間に近い存在である猿と
90%以上は同じであったという結果でした。
そして
眠ったままの遺伝子もあるということも
わかってきたのです。
つまり
我々のからだには
眠ったままの秘められた力があり
その力を目覚めさせる
遺伝子をスイッチオンすることで
様々な力を引き出していた。
そのスイッチオンする力は
自分の思いであるということが
わかったのです。
昔から
人々は、必死に願うときは
手を合わせて
必死で祈り続けました。
祈りは
強い思いがあるからできる
行動でもあり
祈りは
生きるため、どのように生きるかの
強い宣言だと思います。
祈りの語源は
「生宣り(いのり)」であり
「い」は生命力であり
「のり」は祝詞ともとられ
祈りは生命の生きるための宣言とも
考えられるのです。
自分のからだを目覚めさせるのは
医者でも、薬でも、ワクチンでもありません。
生きたい、生きようと思う気持ちであり
生き方を決めれば
からだは決めたように生きられるように
あなたを支えてくれるってことですよね