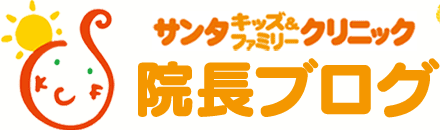「真実の医療」カテゴリーアーカイブ
病気の原因は別のところに
毎日の診療の中で
様々なことを
患者さんから教えられます。
先日、来られたアトピー性皮膚炎の患者さん
なかなかよく治らないということで
とてもお困りの表情で来院されました。
皮膚の状態は
カサカサ、ジクジクのいわゆる
典型なアトーピー皮膚炎の状態ではありませんでした。
これは、原因は皮膚以外にあると直感し
ナチュラルメディカルセンターで行っている
メタトロン、オステオパシーを行いました。
すると予想通り!?
皮膚以上に
小腸と大腸が弱っていることが
わかりました。
最近腸は、
消化機能だけでなく
免疫系にも関与していることがわかってきました。
つまり、
腸が疲弊しているために、
アレルギー反応が起きているのです。
ですから、
この患者さんも
根本原因は皮膚ではなく、
腸が原因だったのです。
いくら皮膚の治療をしても、
よくならなかった訳なんです。
皮膚をよくするために
食事に気をつけ、日常生活を見直し
腸の状態をよくすることが
必要だというこがわかったのです。
病気の原因は、
目に見えるところ、思ってるところではなくて、
今回のように
別のところにあるところ場合もあるのです。
ですから、
診断されてもなかなか
よくならない場合は
別の角度から全身状態を見る
必要があります。
ナチュラルメディカルセンターで行う医療は
良くならないと
日々お悩みの方の
力となれる医療です。
ナチュラルメディカルセンターは
一人でも多くの方が
心から健康と思って過ごせるように
努めてまいります
感情の乱れと病気との関係
メタトロンでは、最後に必ず
感情をチェックします。
こころの乱れ、すなわちストレスが
病気発症に関与していることも多いからです。
実際に
おとなもこどもも
ストレスを抱えて
受診される方が目立ちます。
ストレスが病気を作ることは
昔から言われていることで
内蔵のひとつひとつが
感情と大いに関係があり
東洋医学では七情といって
喜・怒・哀・思・恐・驚・憂があり
それぞれの感情が各臓器を痛めると
されています。
怒は気が上がってしまい肝臓を痛め
哀は気が参じ、肺を胸を締め付けられます
思は欲と同意で、欲は気をドロドロにし
脾臓をいためます。
肝が座っていないと恐れや驚きが強くなります。
恐は腎臓を驚は胆嚢を痛めます。
憂、すなわち不安が大きければ
免疫が下がったり消化不良をおこします
すなわち胃腸の機能が低下するのです。
このように
あなたの思いがからだの不調を
生む結果にもなってしまうのです。
でも、あなたを苦しめる感情は
目には見えません。
そんな時
メタトロンでは、気をつけるべき感情
その感情がからだにどのように影響するかを
教えてくれるのです。
一人で悩まず
メタトロンを利用されてみては
いかがでしょう。
こどものお医者さん
以前、小児科学会で
北原白秋の”子どものお医者さん”
という詩を教えてもらった
「子どものお医者さん」
わたしは子どものお医者です。
わたしの病院、乳母ぐるま、
蜜柑の木のかげ、花畑、
すずしいお池や、ゐなか道、
どこへも巡回いたします。
わたしはお医者の博士です。
泣いてる子どもも療します。
こはれた人形や、きりぎりす、
碧いとんぼのトラホーム、
外科も内科も上手です。
わたしは親切なお医者です。
妹の薬局、バスケツト。
たたいた葉つぱや、薔薇の汁、
おいしいパンくづ、粉ぐすり、
ガーゼも万創膏も持つてます。
わたしは子どものお医者です。
わたしは御礼を受けません。
病気したポチ、弱い鳩、
いぢめられたり、怪我したり、
かはいそな誰でもたすけます。
さあさあ、皆さん、いらつしやい。
どうぞどうぞ、こちらへいらつしやい。
(北原 白秋)
こども達が描いてる
こんな医者になりたくて、医者になった
北原白秋が
僕の気持ちを代弁してくれている。
まだまだ、
至らないことも多く、
日々反省することばかりだけど
もっともっとこんなお医者さんに
なれるように精進しよう
いつまでも
どこまでも
白衣着て、聴診器を携え
みんなと笑顔で手を取り合って
レンゲ、しろつめ草の花咲く
ゐなか道をずっと歩き続けたい
・・・・・と思う
手当の本質
医療の基本は
手当なんだと思う。
小さいころの思い出に
おなかがいたいとき
頭が痛いとき
足をけがをしたとき
病院に行く前
母がしてくれたこと
それは
痛いところに手を当てて、さすってくれると
痛みが軽くなってた気がする。
横に
母が居てくれるだけで
痛みが軽減したのを思い出す。
病気やけがが治ったのは
母のやさしさがあったから
医者の治療が功を奏し
薬が効いたのだと確信している。
母がここが痛いよね、苦しいよね
と温かい手でからだを包みこんでくれる
手当という愛情があったからだと思う。
手当とは
あなたのことを大切に思う気持ちがないと
できないし
あなたのからだを癒やすことはできない。
その人の苦しみを意識しないと
自分のことのように受け入れないと
手当は疎かになる
その人の病を治すことはできない。
それどころか
手当ての気持ちがなければ
どんな軽症の病気であっても
完全に治すことはできないだろう。
「痛いの痛いの飛んでけ」は
本当のおまじない
医療人としても忘れてはいけないおまじない
真のコミュニケーション
消化器外科医の西村元一先生が
自らのがん闘病記の中で
こんなことを書かれていました。
「がんになると
いろんな“フリ”をしてしまいます」と
自分だけでなく
家族も親しいひとも“フリ”を
してしまいます
仕事場では来年があるのが当然のような“フリ”
誰もが悲しんでなどいけない“フリ”
自分も怖がっていない“フリ”
受ける治療に迷いがない“フリ”
“フリ”をすることで
強い自分でいようとして
闘っているのです。
でも
“フリ”をすることで
だんだん
“今までの自分でいられなくなる”
周りに弱みを見せられなくなる自分
もっと悪くなったらどうしようと
不安いっぱいの
本当の自分の気持ちを押し殺して
本当の自分でない自分がそこにはいる。
がんにかかった人でなくても
病気になった人
毎日の診察に訪れた
目の前にいる患者さんは
“フリ”をして
がんばっているのかもしれない。
診察室で
患者さんは
不安いっぱいの気持ちを隠し
理解しようとして
これで元気になれると
安心した“フリ”を
してることがあるかもしれない。
診察室の中でも
“フリ”はせず
自分の気持ちを全てだして
自分らしくいてもらいたい
僕も
患者さんの気持ちを、思いを、不安を
全て受け入れられるよう
“医者”としてだけでなく
“ひと”としても
しっかり向き合いたいと思っています。
病気の時こそ
“フリ”ではない
心の通ったコミュニケーション
本音同志のコミュニケーション
“真”のコミュニケーションが
元気になるために
必要なのだと思います。
大地に触れる
ナチュラルメディカルセンターでは
ますチャクラの状態をみます。
チャクラでご自身の
エネルギーの状態をチェックします。
日々お忙しい生活を送っていると
生活の基盤となるエネルギー
つまり第1、第2チャクラのが
エネルギーが低下しています。
そんな時は
大地からエネルギーを受け取ること
全身で太陽の光を浴びる
外の爽やかな空気を沢山吸う
散歩する
砂浜をできれば裸足で歩くなど
大地の、地球のエネルギーを
全身で感じる時間をもつことを
お勧めします。
大地からのエネルギーを受け取ると
エネルギーが回復します。
疲れがとれます。
元気が出ます。
充実した気持ちで一日が過ごせます。
明朝の目覚めが違います。
今日は秋晴れです。
大自然のエネルギーを感じながら
過ごしてみて下さい。
きっと
明日から充実した日が過ごせますよ。
自然治癒力があがれば
2018年10月ナチュラルメディカルセンターを
開院しました。
その時思いは今も変わらず
みなさんの健康を願って診療しています
【自然治癒力があがれば】
10/1 ナチュラルメディカルセンターを
無事OPENすることができました。
ナチュラルメディカルセンターで行ってる治療は、
自然治癒力を上げる治療です。
自然治癒力があがると、
心身ともに元気になります。
具体的に言えば
①病気になりにくい体になります
②たとえ病気になっても、治りやすい体になります
③飲んでいる薬の量が減ります
④ご自身のもっている100%の力が
発揮できるようになります。
⑤仕事のパフォーマンスがあがります。
⑥学習効果もあがります。
そして何よりも
自然治癒力が上がれば
今という時間がキラキラと輝き出し
からだの、命の大切さを実感し
生き方が変わります。
自然治癒力は誰でも持っている力
その力を引き出すお手伝いをするのが
ナチュラルメディカルセンターで行ってる治療です。
感情の読み方は
先日、以前からサンタクリニックに
受診されていた90歳を超える婦人が
メタトロンを受けられた。
最初に診てから10年は経っているけど
肌つやはよくて
とても90歳には見えないくらい
だったけど
表情は暗く、話す内容は
苦しい、胸が詰まったような気がするし
虫が這ってるような痛みが走ることがある。
どこの病院行っても
原因はわからないし
薬をもらっても一時はいいこともあるけど
また悪くなるのだと。
症状がある時は
どうされているのかと尋ねると
痛い部分をなでていると落ち着いてくるとのこと。
メタトロンで
この苦しい原因が知りたいと
受けることを決断された。
早速メタトロンを行うと・・・・
チャクラなど
エネルギーの流れは悪くない。
臓器も
胆嚢、十二指腸など
食生活における改善点はわかったが
これだけでは
この患者さんの苦しみをとることは難しい。
からだも
90代の状態ではなく、60代の状態。
だから、今も大病もせずにお暮らしなのだろう
ならどうして、こんなに苦しいのだろう?
最後のエタトロンで
感情を診ると
ご自身の感情で
気遣いがでていた。
この意味を見つけようと
実際にからだの状態を診察してみた。
腹部のオステオパシーをしている時に
この気遣いの意味がわかった。
これは
もっと、自分のからだを労ってくれ
気遣ってくれということなんです。
この症状の原因は何だろうと
外にばかりに目を向けるのでなく
もっと自分のからだに気持ちをもってもらいたい。
からだを労る気持ちを持って欲しい。
それが気遣うということなんだと
患者さんのからだが教えてくれたのです。
そのことを患者さんに伝えました。
不調の部分があれば
そこに手を当てて
いつもがんばってくれていることに
感謝の気持ちを伝えてみて下さい。
その気持ちが
自分のからだを気遣うことなんです。
そうお話しすると
すーっと患者さんの目から
一筋の涙が流して、帰って行かれました。
きっとこの患者さんは
からだの思いをわかってくれたと感じた
メタトロンでした。
高い意識のレベルに上げるための方法
今この世に生まれてきた目的が
より高い意識レベルに近づくためだ
とするならば
毎日の生活の中の行動の
すべてが修行ということになります。
僕が考える
日常生活で意識レベルを高める
必要なことを紹介したいと思います。
①憎む、妬む、心配する、怒る、迷う、疑う、不平不満
いらいらする、せかせかする感情を起こさないようにする
もし起きてきたら、すぐ断ち切る。
決してこの感情をひきずらないようにする
②足を知る。簡素な生活をする
③睡眠をしっかりとる。熟睡できる工夫を
④常に正しい言葉を使う。
人を傷つける言葉を使わない
⑤気の悪い、波動の悪い場所や人に近づかないようにする
⑥居住空間を気のいい・美しい場所にする
⑦プラス思考で、楽しく、明るく、おめでたく過ごす。
以上のことを自然に心がけて
生活できるようになれば
きっと成長している自分になっているでしょう
小児科医としての使命
西日本のアレルギーに従事している
小児科医の先生が集まって勉強する。
西日本小児アレルギー研究会に参加した。
大きな学会ではないけど
みんな熱心にアレルギーのいお取り組んでいるので
志は同じだから
お互いの気持ちが通じて
会員同士も仲がよく
とても居心地のいい研究会。
毎年1回の開催で
今回は52回目。
僕も25年以上前から参加させてもらっている。
今回印象に残っているのは
埼玉医科大学医療センター小児科の是松聖悟教授の
講演。
先生とは、大体同年代で
この研究会で何度も顔を合わせて
若い時からエネルギッシュに活動されていた先生。
今回これまでの仕事のことをまとめられた
「小児科医にしかできない、小児科医だけではできない」
というテーマの講演だった。
アレルギーにとどまらず
感染から、育児不安、そして発達障害にまで
小児科医が取り組まないといけない
諸問題に
小児科医として行政、コメディカル、保護者、先生
などとタッグを組んで取り組み
その成果を報告された。
その仕事内容をきいているだけで
多くの人を巻き込み
時流を形成し、社会を動かしている姿が
目に浮かんできた。
と同時に
全ての記録を論文にして
研究の成果を世界に発信している。
若い時のエネルギーを高められた仕事ぶりに
それこそ、小児科医のあるべき姿
The 小児科医だという気がする。
同じスタートにいても
日々の生き方によって
自分とはこん何違う。
先生の生き方はひとつの
小児科医の王道を歩いている。
僕は
医学の教科書になるような
仕事としてはならないけれど
小児科医にの僕だから出来ることを
取り組んでいることに自信を頂いた。
これからもこどもたちのしあわせのために
がんばって歩いて行こうと
背中を押されたような講演会だった