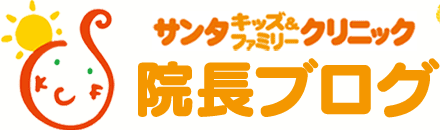年別アーカイブ: 2025
覚醒!?前島ひで子講演会に参加して
知り合いの方に誘われて
日女道の創始者前島ひで子さんの講演会に
出席した。
全くの予備知識もなく参加。
講演が始まると
多くのファン、信者?さんもいらっしゃるのでしょう
熱狂的な大拍手ではじまった。
第一声は
「わたしは神です」
どひゃー、これは宗教?
どうも45年前33歳の時に
いきなり宇宙、神からのメッセージが下りてきて
神の言葉が下りてきて自動書記を行い
その言葉を伝える活動がはじまったそうです。
彼女だけでなく
多くの方が仰るように
神さまは自分の外にいらっしゃるのではなく
一人一人のこころの中にいらっしゃる。
だから
一人一人は自分と違う神さま。
そう思えば憎しみあうことも
争うことも、戦争なんかも起こらない
平和な世界になる。・・・・はず。
みんなのこころの中に神様がいることに
気づきましょう。
その神さまに触れること、気づくことが
覚醒だと仰っていた。
困難の時こそ
その覚醒に気づくチャンスなのだと。
僕も病気を経験したけど
今までと同じ生活に戻れたことを
喜こび、感謝していた。
その後も押し寄せてくる困難。
もっと変われという意味をもらった気がする。
あー僕がやらないといけないこと
変わるべきことがあると思った。
ひょっとしたら、これが{覚醒」と
思えることに出会えた講演会だった。
日本のことをもっと知りたい
医者になると決めた自分
僕は世界を股にかけて働こうと
世界を視野にいれた将来を描いていました。
でも
今は世界に出るよりも
日本の、日本人のよさを知り
世界に伝えようと思いました。
そう思ったのは
大学3年の時
姉夫婦がアメリカにいた時期があり
姉夫婦がいることを理由に
夏休みを利用して
1ヶ月の単独アメリカ旅行をしました。
ワシントン、ニューヨーク、ロサンゼルス、ダラス
ロッキー山脈、イエローストーン国立公園などなど
アメリカ全土、東から西、北から南までまわりました。
旅行の計画はひとりで
地球の歩き方というひとり旅行の本を読み
旅行計画ひとりで立案し
飛行機にのり、バスも使い
ホテルも全て予約からひとりで行いました。
当時から
学校の英語は苦手ではないけど
日常会話なんて、ほとんどできません。
もちろん、今のように
翻訳アプリなどもありません。
そんな僕でも
ひとりで
時にはBOY(少年)と間違えられたり
刺された人をみたりしましたが
計画通り
歩き回って
アメリカ旅行を堪能しました。
今も英語は話せません。
今の僕にはきっとひとりで全てやって行こうなんて
思いませんし
勇気も無いです。
若いからできた経験
親も良く行かせてくれたと感謝してます。
僕の家は
もー列サラリーマン家庭で
家族旅行も
数年に1回行くかどうかの経験敷かない僕が
まずアメリカに行く
東京すら行ったことないのに
ニューヨークやワシントンに行く
これって特別なことだと
しっかりアメリカのことを知ろうと決意し
飛び立ったのを今も憶えています。
全てみようと
どこでも
歩きました、市営バスにのり移動。
自由の女神はフェリーで渡りました。
アメリカの都市の特徴はそれぞれでした。
ワシントンは綺麗だし
ニューヨークではティファニーでお買い物
なんてしゃれこみました。
帰る頃になって
アメリカを色々みて思ったんです。
ニューヨークは知ってるけど
東京も行ってない。
ロッキー山脈の自然に触れたけど
あちこち自然公園や建造物を診た経験をさせてもらった。
けど
僕は日本人なのに
日本のこと何も知らないことに気づいたんです。
アメリカにもいいところが一杯合った
日本は狭い国土だけど
アメリカにないいいところ、素敵なところも
いっぱいあるんじゃなーだろうか?
もう外国はいいや。
僕はもっと、もっと日本のことを
知らないといけないと思って
世界に目を向ける前に
しっかり日本のことを知り
日本のために日本で生きたいと思ったんです。
それから
旅行以外に
外国に行きたいと思ったことは
少しもありません。
最近
アメリカに留学したひとりの青年の
エッセイを目にしました。
そこには、こう書かれていました。
「外国の人はお国自慢が得意です。
自分の国に誇りを持っています。
そして彼らは自国の歴史や文化にも誇りを持っています。
わたしは、高校を卒業していままで
日本で誇れるものを
何一つ学んだことはありません。
自分の国を語れませんでした。
外国の方に対して
私は日本人であることを語れず
なんとなく世界平和を願っているなど
半端な会話で過ごしてました。
今思えばなんと恥ずかしいことだと思ったと
そして、彼は日本に目覚め始めたと」
書かれてました。
まさに
僕がアメリカ旅行から帰国したときの
気持ちも同じでした。
それからは
外国に住もうなんて思いません。
留学しようという気持ちもありません。
日本を知り
日本に生まれたことを誇りにできるように
生きていこうと決意しました。
実際
今当時のアメリカ旅行を振り返り
日本人であることに目覚めるために
アメリカ旅行に行ったような気がするのです
みんなの願い
星新一さんの
「ショートショート」を引き継いで
星新一さんが全国から寄せられた
膨大な作品の中から編んだ
「ショートショート みんなの広場」の中から
八塚顔高さんの「みんなの願い」という作品を
今日は紹介します。
神様の使いが
地球にやって来て
みんなに呼びかけました。
「地球は誕生から
宇宙時間の一周期に達したので
これをお祝いして
神様がみんなのひとつの願いごとを
叶えることになりました。
1週間後に、神様に向かって
自分の願い事を一つだけ念じてください。
その中から一番多かった願い事を
一つ神様が
叶えることになってます。
みんなそれぞれ懸命に考え
1週間後のその日
それぞれの願い事を心に念じました。
神様の使いが再びやってきて
その結果を発表しました。
神様が叶える願い事は
人間以外のほとんどの生物の願いである。
『人間を地球上から
消滅させて下さい』というものに
決定しました。
皆様、次の1周期を目指して
地球を大切にして下さい。
それでは、ごきげんよう。
人間達が
最後に聴いたのは
動物たちの歓喜にも似た喜びの声でした。
これを読んでどう思われましたか?
人間は
いかにも地球上の支配者であるかのように
我が物顔で
動物たちを殺し
地球という環境を破壊し
まだまだ自分達の利益追求に
走っていませんか?
こんな時に
コロナウイルスが登場しても
まだいのちと経済を両天秤にかけ
周りの状況
これまでしてきたことを顧みようともしない人間。
ひょっとして
コロナウイルスは他の生物には広がっていません。
このショートショートのように
動物たちの願いによって
登場したウイルスかもしれません。
ちなみに
人間はたったひとつ叶えてくれる願いに
皆が迷い、一致することもなく
バラバラだったのです。
まさに
我々は、自分のことだけでなく
周りの人が
こどもが孫のこと
そしてこの地球全体の生物のこと
更には
宇宙全体のことも
考えて行動しないといけない
時期になっているのではないでしょうか
明るいこころが病に悩まない日々を生む
人間は全力で生きていくよりも
半分だけ力尽くせばいい。
あとの半分は
自然のめぐみに任せればいい。
弓の矢もそう。
人間はぐっと弓を後ろにひけばいい。
これ以上ひけなくなったら
指を放ち
跡は矢の行く先をみているだけでいい。
毎日の生き方もそう。
できることに力を注ぎ、魂を込め
あとの結果は、元に任せればいい。
日々やるべきことを、やる
なすべきことをなす。
やるべきことをやり抜く生き方こそ
恵ある生き方なんだと思う。
やることはやらずに
人に求めたり
神に頼むのもちがうとおもう。
求める生き方は、やめるべきだと思う。
やるべきことに集中するこことが大事。
朝目が覚めたら
一生懸命働き、汗を流し
やることやったあとの結果は
じっと見つめるだけである。
このように生きる生き方を積み重ねることが
安心の心を生む。
病気の時であっても
生き方は同じ。
やるべきこと、できることをやりきることが
安心のこころを生む
そして
安心の心を生む生き方が
明るい心へとつながり
病気と縁の無い世界へと導いてくれる。
病気と縁のない
明るい心を育てるために
本を読み、色んな方の考えに触れて
自分を見つめ直すことも大事。
そして
成りたい自分に向かって
全集中して生き、働く。
そんな日々を毎日積み重ねれば
病気と縁の無い
明るいこころでいられる。
ルノワール~おとなの闇を知った少女~
ルノワールという映画を観た
この映画は1980年代後半の夏が舞台。
闘病中の父と仕事に追われる母と暮らす11歳の少女の
ひと夏の物語。
父は闘病中、母は忙しく
父の迫り来る死の影で
ギクシャクする家庭のなかで
自分の居場所
そして自分の思いをわかってくれる人を
求めている少女。
その時期はやった超能力、そして伝言ダイヤルに
孤独から救ってくれるものを
求めるひと夏の旅。
おとなは自分の気持ちをわかってくれないし
逆に甘い言葉で誘惑する
おとなの裏側を知る。
と同時に両親の純粋な
自分を愛する気持ちを確認した少女。
父親が亡くなり
ぽっかり穴を埋めるように
旅に出た親子
その二人がテレパシーを使い
こころが通じ合うことを確認した母子。
きっと二人で
これからの人生を歩み続けてくれることを
象徴された場面で終わった。
この映画は
多くのカットが
次から次に映像として現れる
言葉は少ないが
こころから生まれた背景を
映し出した光景として
強く語りかけてくる。
見終わった後に、深く考えさせられる
映画だった。
意識が現実をクリエイトしている
人は
死に直面するようなことがあっても
まずはそのことを受け入れることが大事。
受け入れると、開き直りがおこり
今までの自分の殻から脱皮し
様々なことを受け入れるようになったと。
受け入れた監督は
病気を受け入れ
様々な治療を受け入れ
そして
治そうという気持ちが強くなったそうです。
と同時に
人に治してもらおうではなく
治ろう、治そうという意識するようになったそうです。
その思った瞬間に
からだが大きく変化しだし
意識が治ると思えば思うほど
日に日に治り始め
ついには
脳腫瘍が消え、完全に生還できたと
話をされました。
意識が動くと
癌のような大病でさえ
治すことができるのです。
意識が大事なことは
実は医学の世界でもしられています。
アメリカの整形外科医が
こんな実験をされてます。
膝が悪くて入院中の患者さんに対して
手術をすること説明した患者さんに
実際に手術をした患者さんの群と
実際には手術しなかった患者さんの群と
2つに分けて治療しました。
その結果は・・・
なんと
実際に手術しなかった患者さんの
3割が実際に治ってしまったのです。
つまり治ると意識すると
自分のからだを治すというスイッチがONになり
実際に治ってしまうのです。
これを医学的に
”プラシーボ効果”と言います
もし、病気になった時
自ら治そうという意識が
とても大事と思うのです。
病気の時だけでなく
どんな困難な時にも
自分を信じて
治る、良くなると意識してもらいたいのです。
意識が現実をクリエイトします。
病気は医師が治すのではなく
あなたの意識、こころが治すのですよ。
恐怖に対する対処法
こころの中に
恐怖心が一旦芽生えてしまうと
人間はそれをとめることはできないと言います。
特に死に対する恐怖心が生まれると
死の実態がつかめないために
恐怖心が増すことになります。
ですから
恐怖心が生じた時には
恐怖心を押さえ込もうとせずに
その恐怖をできるだけつぶさに
観察するのがいいという。
なぜ怖いのか
なぜ怖いという気持ちが今湧いたのか
死の何が怖いのか。
怖いと思う気持ちの本体は何なのか?
生じた恐怖心を避けるのでなく
その恐怖心そのもの、恐怖の思いを
逃げずに向き合うことが
大事なのかもしれない。
恐怖心について考え続けていると
だんだん恐怖心そのものが薄まるはずです。
恐怖心をだんだん客観視できるようになり
怖がっている自分さえも
客観的に観る自分が生まれてきます。
なぜなら
考え事に集中している時は
感情は意識の後方へと撤退するからです。
自然のパワーを意識して
自然を意識していければ
健康で過ごせます。
例えば
アトピー性皮膚炎などの
アレルギー疾患が心配なら
ビタミンDを頑張って摂取するより
食べ物を気にしながら過ごすより
家の中を消毒するより
太陽の光をいっぱい浴びて
家の外で泥んこまみれになって遊び
その土で育った野菜を
しっかり食べればいい。
降り注ぐ無限の太陽のエネルギー
大地からのエネルギー
すなわち自然の恵みをからだいっぱい
取り込めば
皮膚も肺も腸も自然と整ってくる。
地球に生まれ
地球の恵みをからだいっぱい受け取れば
病気のことなど何も心配いらないと思う。
大事なこどもの遊び
近頃のこどもたちは忙しい。
かつては学校から帰ったら
昔は宿題したら、遊びに行っていたけど
今のこどもたちは
宿題済めばいいというわけではなく
塾や習い事が合って自由時間は少ない。
友達と遊ぶ時間も合わないし
遊ぶ場所もないし
だから、一人でゲームで遊ぶ時間が
増えたのではないのでしょうか?
遊ばなくなったこどもたちには
こどものうちに遊ぶ時間を
もっととって欲しいと思います。
というのは
遊びは、相手の力を見極めながら
ルールを作りを考えていきます。
つまり、相手の体力や気分などを
推し量らないと
一緒に遊べなくなります。
だから
遊びを通して
相手を思いやる感性や
一緒に過ごすためのルール作りを
学んでいるのです。
そして
ルール作りが上手くいくと
その遊びは楽しくなって
こどもたちの笑い声が響く笑いになるのです。
大きな声で笑うと、気持ちもスッキリ
友情や、もっと楽しく生きていこうという
前向きな気持ちも生まれます。
こどもの遊部ことは大事なこと。
こどもたちに是非遊ぶ時間と遊ぶ場所を
提供するのがおとなの役目なのかもしれない。
人生はテーマパーク
人間の人生は
こどもがテーマパークで遊んでるような
感じに陥ることがある。
テーマパークと一口で言っても
広いところもあるし
狭いところもあるし
いろんな遊具があるところもあるし
冒険を体験するところ
ファンタジーや夢を感じるところ
恐怖を感じるところ
過去を感じるところ
未来を感じるところ
その内容はさまざま。
人生のテーマパークは
出生エントランスからはじまって
学校ジャングル
人間関係の迷路
就職クルーズ
結婚アドベンチャー
おとなファンタジー
老いの館
と様々なエリアを体験していく。
この巨大なテーマパークを
如何に過ごすかは
ひとりひとりの思い、心持ちで
異なると思う。
閉園して人生のテーマパークを退出するのは
死を意味する。
ですから
死に日を迎えるまで
人生のテーマパークを楽しんでいきましょう。